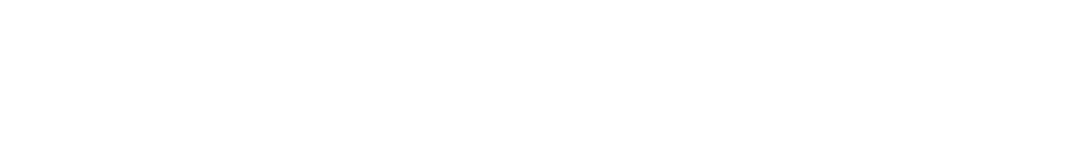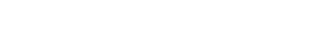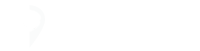神奈川歯科大学との系属校化に向けた連携授業「医療時事」がスタート!
2025/09/03(水)
本校では、医療系進学を希望する2年生を対象に、学校設定科目「医療時事」を開講しています。この授業では、医療に関する旬の話題を取り上げ、国語化・理科・社会科の教員が連携して、基礎知識から小論文指導までを一貫して行っていました。
今年度は、神奈川歯科大学との系属校化に向けた新たな取り組みとして、大学の先生方に授業計画段階から関わっていただき、実際の講義にも出講していただいています。以下は、これまでの全4回の授業内容です。
第1回「院内感染」
担当:短期大学部看護学科 渡邊好江准教授(成人看護学・クリティカルケア看護学)
講義では、COVID-19の感染拡大期の経験も踏まえながら、「見えない敵」とどう向き合ってきたか、また院内感染対策における基本動作(手指消毒など)の重要性が語られました。
事前に、本校理科教員より感染症に関する基礎知識を学んでいたこともあり、生徒たちは講義に強い関心を示し、講義後には教卓を囲んで意見交換する姿も見られました。

第2回「インフォームドコンセント」
担当:短期大学部看護学科 教務担当教学部長 棚橋泰之教授(基礎看護学)
「インフォームドコンセントは、いつ頃から、なぜ必要と言われるようになったのか?」という問いかけから始まった講義では、患者の自己決定権や医療者のパターナリズムについても議論されました。
棚橋教授は生徒一人ひとりの意見に丁寧に耳を傾け、全体に共有してさらに問い返すという、まるで大学のゼミのような深い対話が展開されました。

第3回「臓器移植」
担当:短期大学部看護学科 吉越洋枝准教授(成人看護学)
身近なテーマである臓器移植について、①脳死下②心停止下③生体移植の3種類を学び、脳死判定に用いられる「対光反射」測定をペアワークで体験しました。
生徒たちは瞳孔スケールやペンライトを使いながら、驚きと笑顔あふれる体験を通して臓器移植への理解を深めました。講義後の感想では、「家族とこのテーマについて話してみたい」「移植コーディネーターという仕事を初めて知った」など、多くの学びが共有されました。

第4回「再生医療」
担当:歯学部臨床科学系歯科保存学講座 小牧基浩主任教授(歯周病専門医・指導医)
小牧教授は、ギリシャ神話のプロメテウスの話から再生医療の可能性を語り始めました。細胞や組織を用いて失われた臓器を再生するという最先端医療の可能性とともに、その倫理的課題や、看護師として果たすべき役割についても熱く語られました。患者の期待と医療現場の現実とのギャップを埋める看護師の役割、そして「納得して選ばれる医療」への支援者としての責任が強調され、生徒たちは医療の未来と進路について、深く考える機会となりました。
おわりに
「医療時事」の授業を通じて、生徒たちは単なる知識の習得にとどまらず、社会の中で医療とどう向き合うかを考え、自らの言葉で発信する力を養っています。神奈川歯科大学の系属校という新たなステージを迎えるにあたり、専門家の直接的な指導によって、学びの深まりがより一層進んでいることを実感しています。
今後も、より多くの医療現場の声とつながりながら、生徒一人ひとりが「医療の未来」を自分の事として捉えられるような教育を進めていきます。